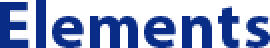CLOSE
About Elements
私たち田中貴金属は、貴金属のリーディングカンパニー。
社会の発展を支える先端素材やソリューション、
それらが生まれた開発ストーリー、技術者たちの声、そして経営理念とビジョンーー
Elementsは、「貴金属を究める」をスローガンに、
より良い社会、豊かな地球の未来につながるインサイトを発信するWEBメディアです。

資源を循環させる経済システムがサステナビリティとビジネスの両立の鍵に

持続可能性追求こそ、事業リスクへの最適解
ものづくり企業のサステナビリティ
貴金属のリーディングカンパニーとして、産業用貴金属製品、資産用貴金属商品、宝飾用貴金属商品の3つを柱として事業を展開している田中貴金属グループ。同社のサステナビリティ・広報本部の平尾彰英本部長が、ESG投資やサステナビリティ経営を専門とする夫馬賢治氏を迎え、ものづくり企業に求められるサステナビリティの取り組みなどについて語り合った。
アドオンでの取り組みにより「やらされ感」が発生
■夫馬 欧米に比べて日本企業のサステナビリティへの取り組みは10年遅れていましたが、原材料の調達問題による供給リスクなどへの理解が進み、大企業を中心に急速に進展しています。
■平尾 実際、ここ数年で当社グループが産業用製品を供給する企業のお客様の意識が急激に変化していると感じます。鉱山由来ではない金属素材へのニーズが高まり、一層の対応が求められているのです。

▲TANAKAホールディングス株式会社 常務執行役員 サステナビリティ・広報本部 本部長
平尾 彰英 氏 ※
■夫馬 原材料の問題はやはりビジネスインパクトが大きいですよね。ただ、日本のサステナビリティは本業を通じて貢献するといったアドオンとして広がったため、「やらされ感」が強い企業もあります。今の市場環境は続かないことを認識し、事業を変えていかなければ企業の未来はありません。
■平尾 事業継続の屋台骨として考える必要がありますね。そもそも当社は、産出量が限られた貴金属の取り扱いを事業ドメインとしていますから、サステナビリティへの取り組みは重要な事業課題です。企業活動を持続するため、貴重な資源をいかに利用していくかを課題とし、創業以来向き合ってきました。実際に創業200年となる2085年を見据え、持続可能な社会や超長期の企業経営を目指す「TANAKAルネッサンスプラン(TRP)」でも、サステナビリティをキーワードとしています。限りある資源である貴金属を超長期視点で大切にし、貴金属の価値を提供していくことが当社の使命と考えています。
■夫馬 世界を見ても2050年までを長期としている企業が多い中、62年後を見据えていることに驚きました。長期的に見るほど市場環境の変化は大きくなり、現状維持は困難になります。長期的視野で企業のあり方を考えることは持続可能性の追求において非常に重要です。実際、金属の中でも需要の伸びが期待できる一方で、採掘による環境や人権などの問題がフォーカスされてきた「金」の取扱量が多い田中貴金属さんでは、資源の再利用を徹底するなど、リスクを事業機会に変える努力を長年されていると思います。
サステナビリティに有効なサーキュラーエコノミー
■平尾 貴金属のリサイクルは、創業時から当社のDNAに刻まれてきたものです。全社員が「地金はお金」を合言葉に、作業服に付着した極微量の地金も丁寧に回収し、再利用しています。こうしたリサイクル力を生かして、貴金属資源の循環的な利用を図り、廃棄物を少なくする経済システム「サーキュラーエコノミー」の実現に取り組んでいます。
■夫馬 循環型社会とビジネスを両立させるサーキュラーエコノミーに関しては、様々な産業で動きが出ていますね。

▲株式会社ニューラル 代表取締役 CEO 信州大学特任教授
夫馬 賢治 氏 ※
■平尾 ええ、当社でもそのために事業工程を整理し、モニターすべき指標を設定しています。その1つが外部調達地金1tあたりの利益を示す「資源生産性」です。環境視点での“稼ぐ力”を可視化します。「循環利用率」は総地金投入量に占める自社のリサイクル地金量であり、約8割で推移しています。CSR報告書にこれらを開示し、改善していくことでサーキュラーエコノミーの実現を目指します。
■夫馬 先ほどのお話にもありましたが、再生素材のニーズは急激に高まっています。それに伴い、リサイクルの土壌も整ってきていますが、課題となるのは“回収”です。使用後の製品がどこに積み上がっているのか見えにくい実態があります。
■平尾 回収でいうと、当社では大きく2つの方法があります。貴金属製品を供給しているデバイスや消費財メーカーなどのお客様から端材、未使用素材などを回収するルートと、市場に出た家電や通信機器、いわゆる都市鉱山から回収業者を通じて調達するルートです。貴金属を循環させるため、回収システムの構築にも力を入れています。
課題も開示することで“グリーンウォッシュ”を回避
■夫馬 サステナビリティを重視する企業は増えてきましたが、日本には言わないことを美徳とする文化があり、積極的に発信しない傾向にあります。しかし、当事者である企業が自ら発信することは、多くの人々の理解を得ることにつながります。ただ、課題を隠し、全部できているかのように印象づける“グリーンウォッシュ”に向けられる視線は厳しい。それを防ぐ方法は透明性です。現状の課題までを挙げ、今後の方針を語ることが重要です。
■平尾 課題と方針の開示が大切なのですね。当社では循環型社会への貢献に加え、水素エネルギー関係製品など環境対応素材も提供していますが、一方ものづくりの現場では環境負荷を避けられない面もあり、脱炭素への取り組みを急ぐ必要があります。そこで、22年に「田中貴金属グループ カーボンニュートラル宣言」を表明し、50年にCO2排出量実質ゼロを目指すことを宣言しました。社長をリーダーとする全社横断プロジェクトチームを立ち上げ、工場でのエネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの導入など、カーボンニュートラルの実現に向けた対策を推進しています。
※ 社名/出演者プロフィールはインタビュー当時の情報になります。
この記事は、「日経BP(2023年3月10日)」に掲載された記事広告を転載したものです。